おすすめのプロモーション
深刻なホーチミンの地盤沈下、一部地域では1m近く沈下

<写真:tuoitre.vn>
ホーチミン市で地盤沈下が加速し、海面上昇の2倍に達していることが明らかになった。
8日に開催されたホーチミン市資源環境大学のセミナーで発表された調査結果によると、特にビンタン区とビンチャイン郡での地盤沈下が顕著で、10年で約1m近く沈下した地点もある。
セミナー「ホーチミン市における地盤沈下の現状と持続可能な経済発展への影響」にて、ホーチミン市資源環境局は1990年代から地盤沈下が市内で始まったことを報告した。
日本国際協力機構(JICA)による調査では、ホーチミン市全体で年間2~5cm、商業施設が集中する地域では7~8cmの沈下が確認されている。
この速度は海面上昇である年間約1cmの2倍に相当する。
2013年に政府は国土交通省と協力し、ホーチミン市の沈下対策と冠水防止プロジェクトを開始した。
地図測量局が2005年から2014年にかけての高度データを比較したところ、10年間で10cm以上沈下した地域が多く、影響が広範囲に及ぶことが明らかとなった。
沈下地域には、ビンチャイン郡やビンタン区南部、8区、7区西部、12区東部などが含まれ、その面積は239k㎡に達する。
特に沈下が深刻な地点として、ビンタン区アンラック街区の文化センターが10年間で73.3cm、同地区のタンタオ工業団地が73.2cm沈下している。
また、ビンチャイン郡タンタック街区の医療センターでは44cmの沈下が報告された。
2014年以降も沈下は続き、ビンタン区の沈下は81.8cm、ビンチャイン郡では48.8cmに増加している。
専門家によると、ホーチミン市の地盤沈下には4つの主な要因が考えられる。
まずは軟弱な地質であり、このため自然に沈下する地域が多い。次に、人為的な要因として交通量の多い地域では大型車両の通行による影響が大きいとされる。
また、建設工事も一因とされるが、これは主に工事中の一時的な影響であり、その後は沈下が安定する傾向にある。
さらに、地下水の過剰採取も要因とされ、2010年以前はゴーバップ区、タンビン区、12区などで顕著であったが、現在は地下水採取が制限されている。
これらの地盤沈下は、高潮や海面上昇の影響と相まってホーチミン市の沈下を加速させている。
地盤沈下は経済や生活環境に深刻な影響を及ぼすものであり、広範な浸水リスクへの対策が急務である。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。









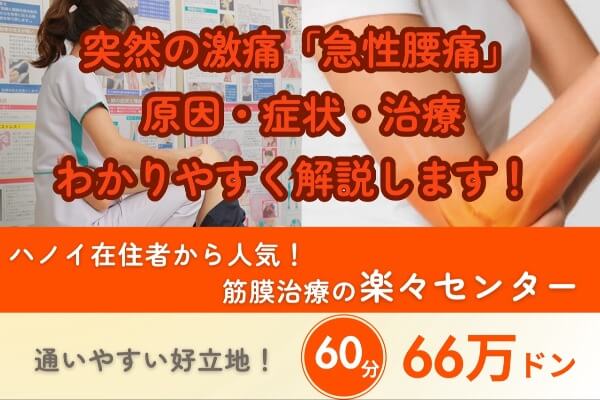






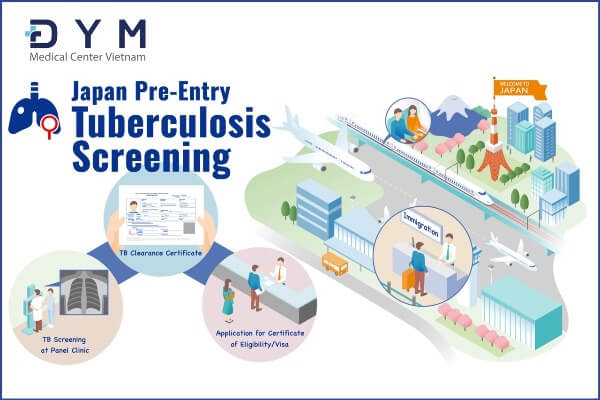


















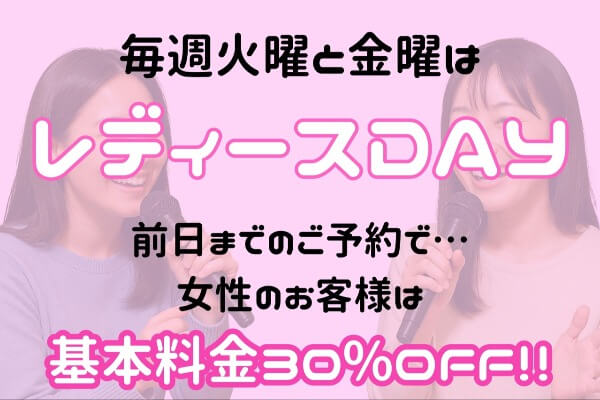



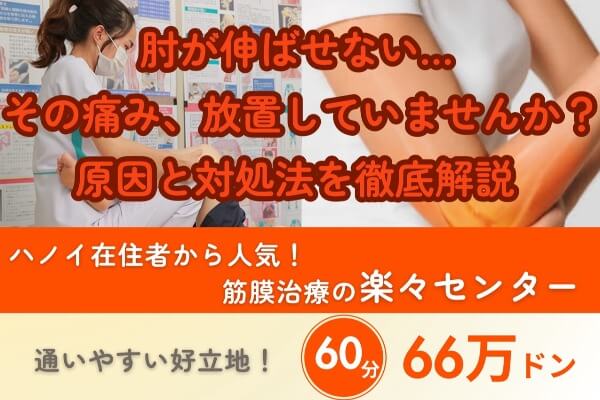




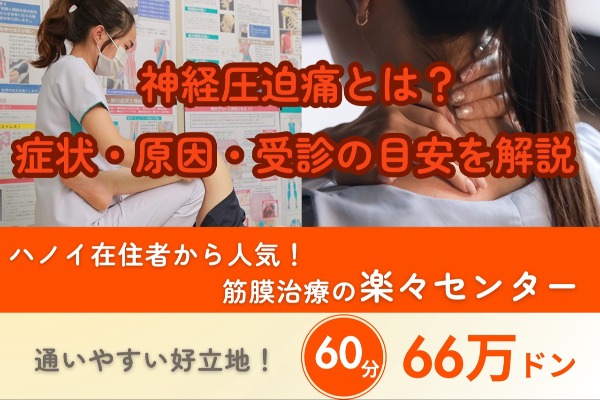

























![[食肉卸]独占輸入・飲食店必見! 宮崎のブランド鶏をHCMCで](https://image.poste-vn.com/upload/vn/lifetip-article/lifetip_article_20250829_1756435949.8758.jpeg)











