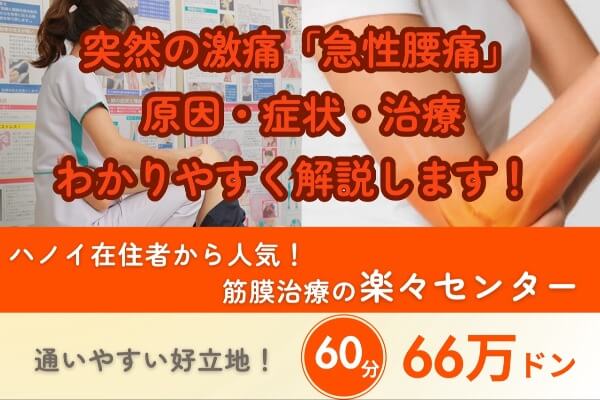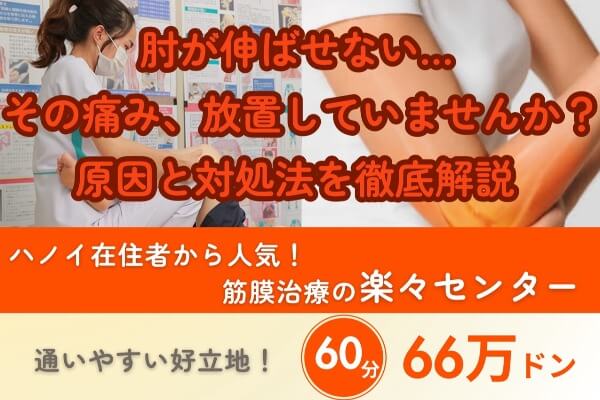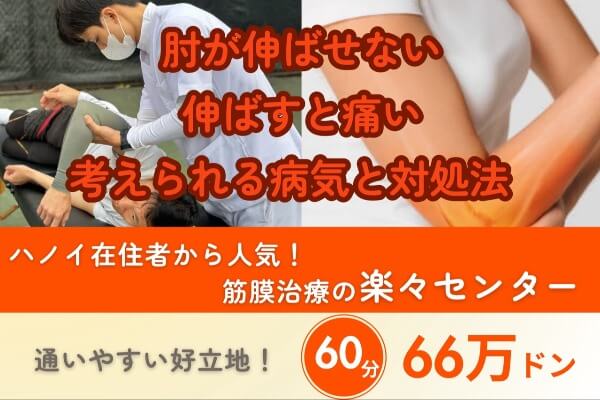おすすめのプロモーション
ベトナムの大気汚染問題、ホーチミン総死亡数の約13.5%に関与

<写真:vienktxh.hanoi.gov.vn>
国連環境計画(UNEP)によると、世界では毎年約700万人が大気汚染に起因する疾患や感染症で命を落としており、その数は交通事故の死亡者数の5倍以上、新型コロナウイルス感染症の公式死亡者数をも上回る。
世界保健機関(WHO)の調査では、2016年にベトナムで心疾患、脳卒中、肺がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺炎によって亡くなった人は6万人を超え、その多くが大気汚染と関連していることが明らかになっている。
最も危険な大気汚染物質には、微小粒子状物質(PM2.5)、地表オゾン、二酸化窒素(NO₂)、ブラックカーボン(BC)、メタン(CH₄)が含まれる。
PM2.5は調理や暖房時の不完全燃焼、廃棄物や農業残渣の焼却、工業活動、交通機関の排ガスなどから発生し、肺や血流に深く浸透することで心疾患や肺疾患、脳卒中、がんのリスクを高めるとされる。
ホーチミン市科学技術連合会のグエン・バン・フオック教授らの研究によれば、2017年の同市における総死亡者数1397人のうち、大気汚染に関連する心疾患・肺疾患による死亡者は841人で60.2%を占めていた。
内訳として、虚血性心疾患による死亡者が483人で34.6%、肺がんによる死亡者が73人で5.2%であった。
特にPM2.5が原因と推定される死亡者は1137人で81.3%に達し、次いでNO₂が171人で12.3%、SO₂が88人で6.4%と続いた。大気汚染がホーチミン市の総死亡数の約13.5%に関与していると考えられる。
ベトナムの環境問題に詳しい弁護士チュオン・アイン・トゥ氏によれば、ハノイ市やホーチミン市をはじめとする都市部では大気汚染が深刻な問題となっている。
2020年に施行された環境保護法には、企業や産業団地に対する排出規制の強化や交通機関の排ガス基準の設定などが盛り込まれているが、実際の運用には課題が残るという。
特に道路の粉じん、建設工事の排出物、伝統工芸村や産業団地からの煙、廃棄物・稲わらの焼却、化石燃料を使用する交通機関など、大気汚染の主要な発生源に対する取り締まりが不十分であり、法の厳格な適用が求められている。
ベトナム政府は2025年に大気汚染の改善に向けた包括的な対策を打ち出す予定である。1月8日に開催された中央政府と地方自治体の合同会議において、グエン・ホア・ビン副首相は「都市部の大気汚染を改善するための国家戦略を策定・実施する」と表明した。
また、ドー・ドゥック・ユイ天然資源環境相は「過去10年間でハノイ市やホーチミン市における大気汚染の悪化が顕著になっている」と述べ、排出源の管理強化やクリーンエネルギーの導入推進が急務であるとの認識を示した。
大気汚染は健康への深刻な影響にとどまらず、経済活動や社会全体にも負の影響を及ぼす。政府や地方自治体の積極的な対応に加え、企業や市民一人ひとりが環境保全の意識を持ち、持続可能な都市環境の実現に向けた取り組みを進めることが求められている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。