おすすめのプロモーション
ホーチミンにおける肥満、塩分過剰摂取の深刻な実態

<写真:laodong.vn>
ホーチミン市疾病管理センター(HCDC)の報告によれば、同市では年齢層を問わず肥満率が上昇傾向にあり、住民の塩分摂取量も世界保健機関(WHO)の推奨基準を大幅に上回っている。
2024年、ホーチミン市では医療部門の取り組みにより、母子の栄養不足の改善が進められた。
5歳未満の子どもの低体重率は4.5%、発育阻害率は5.8%と低い水準を維持しており、小児や妊婦を対象とした微量栄養素欠乏症対策も効果を上げている。
その結果、臨床的なビタミンA欠乏症の報告はなかった。
一方で、都市化の進行や座りがちな生活習慣、栄養に関する認識不足といった課題が依然として残る。
野菜や果物の摂取不足、塩分や脂肪の多い食事が肥満率の上昇に拍車をかけ、生活習慣病のリスクを高めている。
HCDCの報告によれば、ホーチミン市民の1日あたりの塩分摂取量は平均8.5gに達しており、WHOが推奨する5g未満を大きく超えている。
過剰な塩分摂取は高血圧を引き起こし、心血管疾患や心不全、腎不全、骨粗しょう症、胃・十二指腸潰瘍、消化器系のがんリスクを高める。
ホーチミン市人民委員会の報告によると、市内の5歳未満児の肥満率は2017年の11.1%から2022年には13.6%へと上昇し、2020年の全国平均11.1%を上回っている。
特に学齢期の子どもにおける肥満の増加が顕著で、2014年の41.4%から2020年には43.4%に達した。
2020年の全国平均26.8%と比べても高く、小学生の肥満率は56.9%と最も高い数値を示している。
18~69歳の肥満率も2020年には37.1%に達し、全国平均の20.6%を大きく上回る結果となった。
2025年にホーチミン市当局は栄養教育の強化や食習慣改善のための行動変容の促進、家庭や集団給食における栄養バランスの向上を進める方針である。
また、栄養政策の監視・評価を継続し、市民の健康状態の改善に取り組む。
WHOによれば、肥満は骨・関節疾患や2型糖尿病、心血管疾患のリスクを高めるだけではなく、少なくとも13種類のがんとの関連も指摘されている。
肥満や生活習慣病の増加によって社会的な医療負担の増大も懸念されており、今後の適切な対策が求められる。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。






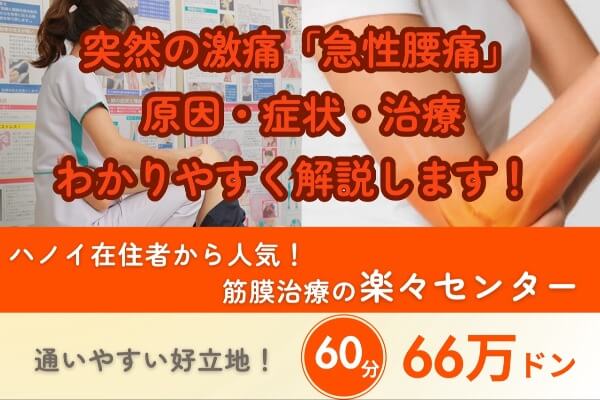






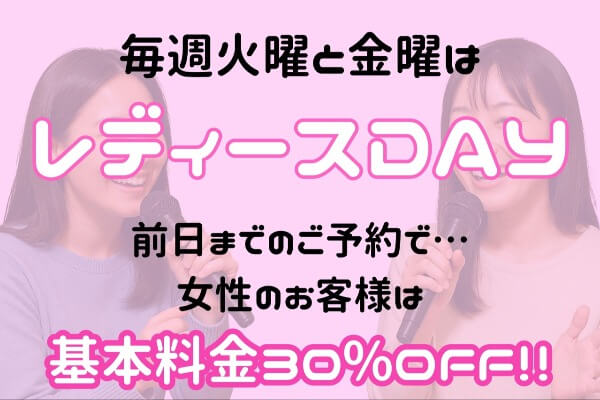

















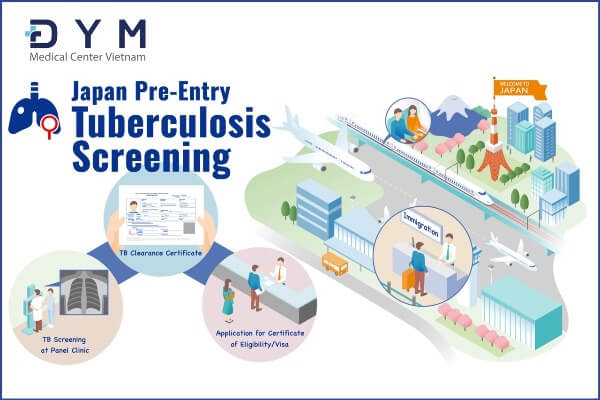





















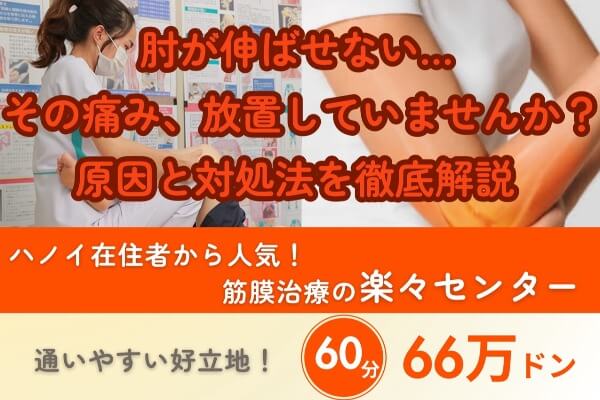












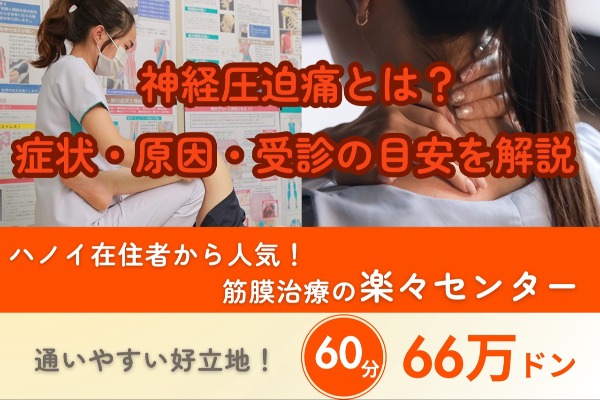


![[食肉卸]独占輸入・飲食店必見! 宮崎のブランド鶏をHCMCで](https://image.poste-vn.com/upload/vn/lifetip-article/lifetip_article_20250829_1756435949.8758.jpeg)












