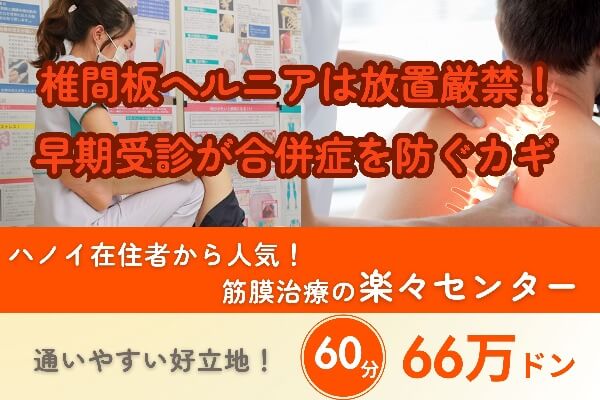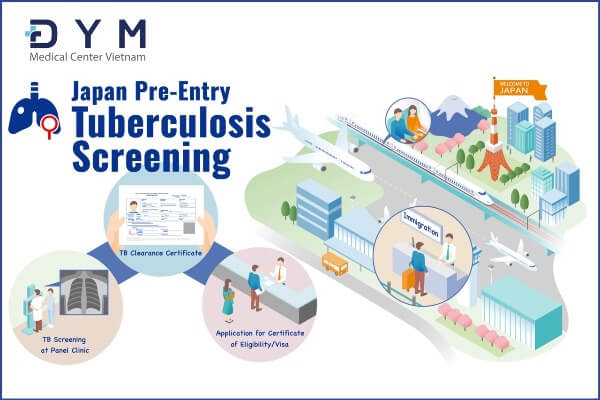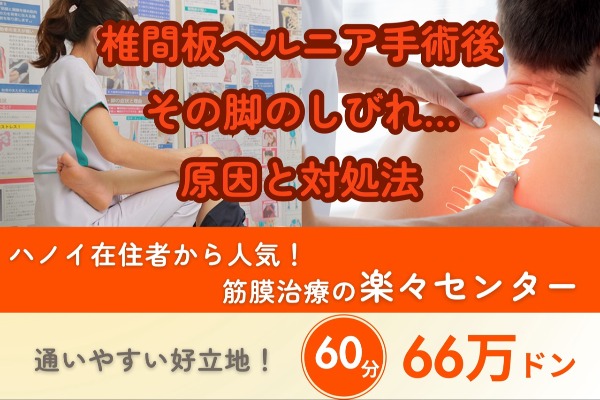おすすめのプロモーション
物価上昇の実感と統計の乖離、家計への影響が深刻化

<写真:markettimes.vn>
ベトナム政府が発表する消費者物価指数(CPI)は前年比で3%強の上昇にとどまっているが、ホーチミン市をはじめとする都市部の住民の間では、実際の生活費がそれを大きく上回っているとの認識が広がっている。
家賃や学費、食費の高騰により、実際の支出が前年同時期と比較して3割以上増加したという声も聞かれる。
統計総局のグエン・チュン・ティエン副局長によれば、CPIと体感インフレ率の乖離はベトナムに限らず、欧米や日本でも見られる世界共通の現象であるという。
その要因として、食品・電気・ガソリンなど日常生活に直結する品目の価格変動が、全国平均で算出されるCPIよりも家計に大きな影響を与えている現実が挙げられる。
CPIは全国平均の家計支出構造を基に752品目を対象として算出されるが、個々の家計の実態を必ずしも正確に反映しているわけではない。
特に、ガソリン価格のような即時的な変動には反映の時間差があり、都市部特有の支出である住宅ローンや塾代などはCPIに含まれていない。
統計上、食品・住宅・交通など7分野で家計支出の86%を占めており、特に低所得層においては生活必需品への支出割合が高いため、価格上昇が生活に直撃しやすい。
生活費の圧迫は消費の抑制を招き、衣料品、家電、観光といった非必需品の需要が減少すれば、経済全体への悪影響も懸念される。
実際、家計最終消費支出はGDPの55%以上を占めており、その影響は看過できない。
経済専門家は昨今の物価上昇の背景として、地代の上昇、新たな税制度、需要減少に伴う小売業者の価格戦略などを挙げている。
これらの要因による価格上昇は一時的で持続性に乏しいとされており、かえって市場の購買力をさらに弱める可能性があるとの指摘もある。
さらに、CPIが前年比で示されるという統計上の特性により、長期的な価格上昇の実感との間にギャップが生じやすいことも問題視されている。
仮にCPIが毎年3%上昇を続けた場合、10年で物価は34%上昇することになり、賃金の伸びがそれに追いつかなければ、実質的な購買力は大きく低下する。
一部の専門家は、全国一律のCPIに代わり、都市部と地方、あるいは所得層ごとに細分化された指標の導入を提案している。
また、価格統制政策については競争市場を歪める可能性があるとして否定的な見解を示し、企業によるコスト削減努力の促進を重視する立場をとっている。
一方で、交通や電力といった独占的なインフラ分野に関しては、国家による積極的な監督とコスト管理の重要性が強調されている。
総じて、ベトナム経済における3%程度のインフレ率自体は制御可能な範囲にあるとされるが、問題は生活必需品の価格上昇に賃金の伸びが追いついていない点にある。
専門家は「低インフレであっても生活が苦しければ、国民の不安は払拭されない」と警鐘を鳴らしている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。














![[飲み放題付き]値段変わらず選べる4種のコース!まる名物を堪能♪](https://image.poste-vn.com/upload/vn/promotion-event-article/promotion_event_article_20250917_1758103973.8193.jpeg)