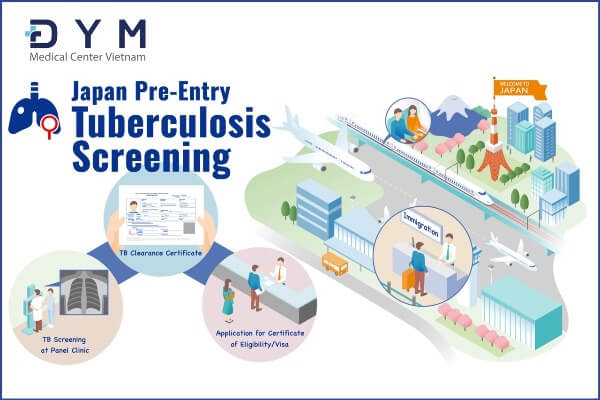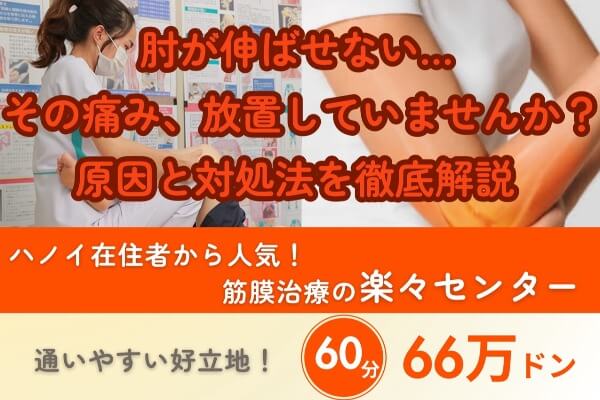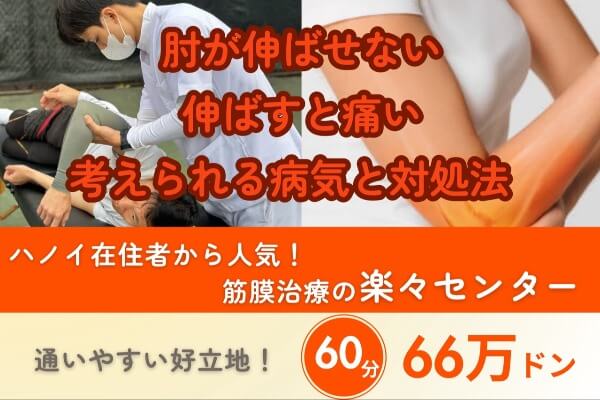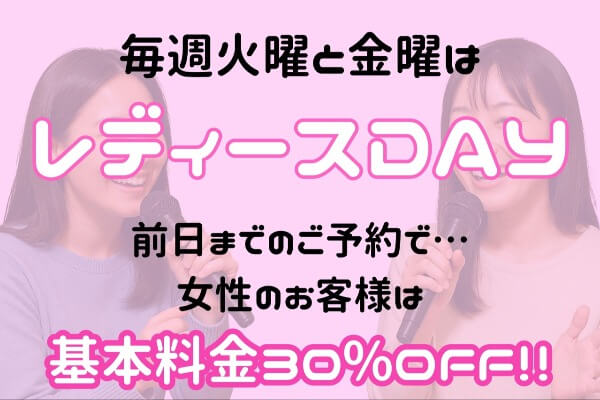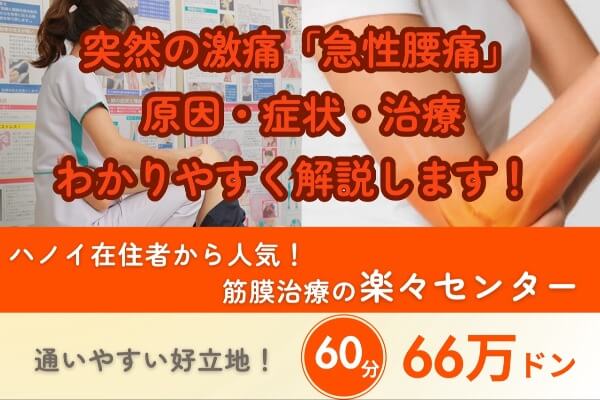おすすめのプロモーション
ホーチミンの出生率低下、若年層の住宅負担が影響

<写真:lifestyle.znews.vn>
ホーチミン市において、若年層が住宅を購入する際の経済的負担が、子どもを持つか否かという人生の重要な判断に大きな影響を与えている。
9月24日にベトナム保健省は「2030年までの地域・対象別出生率調整計画」の改訂案に関する意見交換会を開催し、こうした課題が浮き彫りとなった。
同省の報告によれば、全国の合計特殊出生率は2021年の女性1人あたり2.11人から、2024年には1.91人へと急激に低下しており、過去最低水準にある。
特に都市部での出生率低下が顕著であり、ホーチミン市、カントー市、タイニン各市が全国でも最低水準に位置している。
中でもホーチミン市は、女性1人あたり約1.42人にとどまっている。
ホーチミン市当局が実施した簡易調査によると、出生の決断に影響を与える主な要因として、「医療」「教育」「住宅」「保育サービス」が挙げられている。
ホーチミン市はこれらの課題に対応するため、結婚前の健康診断や妊娠前ワクチン接種の補助、乳幼児および学童への健康検査支援、不妊治療費の補助といった施策の導入を検討している。
中でも住宅の取得が困難であることは、若年層にとって深刻な問題であり、子どもを安心して持つことへの心理的障壁となっている。
この現状を踏まえ、市は所得税の減免、社会住宅の整備、長期賃貸への補助などの住宅支援を、出生促進政策と連携して段階的に進めていく方針である。
出生率の低迷が続けば、2030年には「人口黄金期」が終わり、2042年には労働年齢人口がピークを迎えると予測される。
さらに、2054年以降は人口の減少が始まる可能性も指摘されている。
こうした人口構造の変化に対応するため、ホーチミン市は2025年から2030年までの期間に、合計特殊出生率を女性1人あたり1.6人程度へ引き上げることを目標に掲げている。
今後は医療・教育・住宅・保育を一体的に捉えた総合政策を通じて、出生率の回復を図る構えである。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。