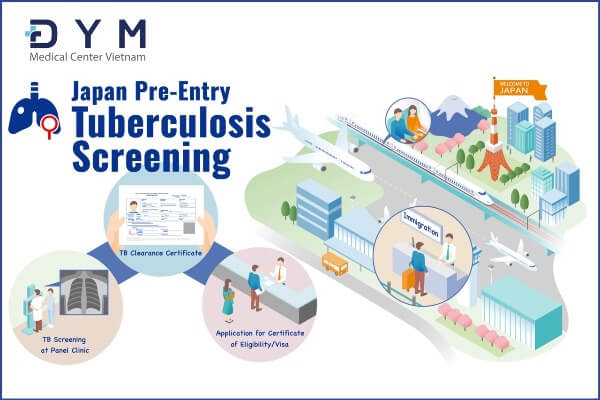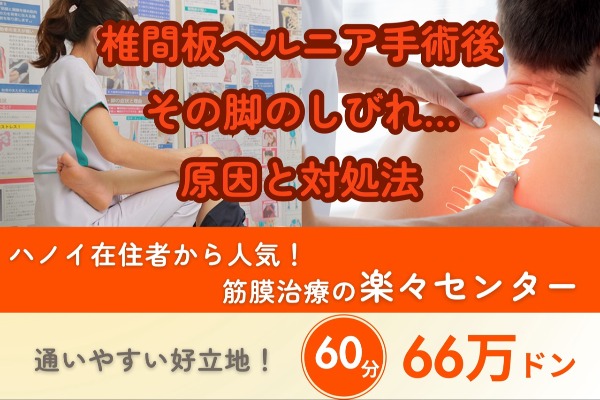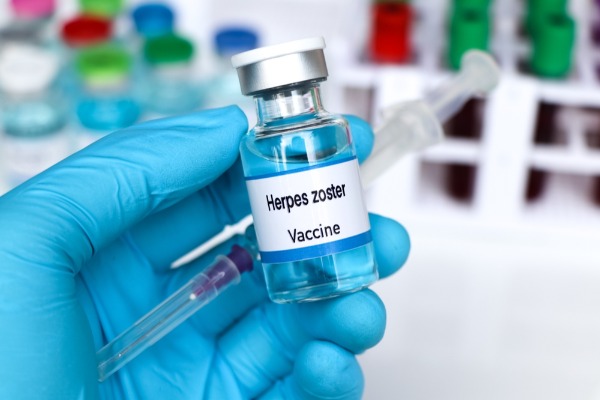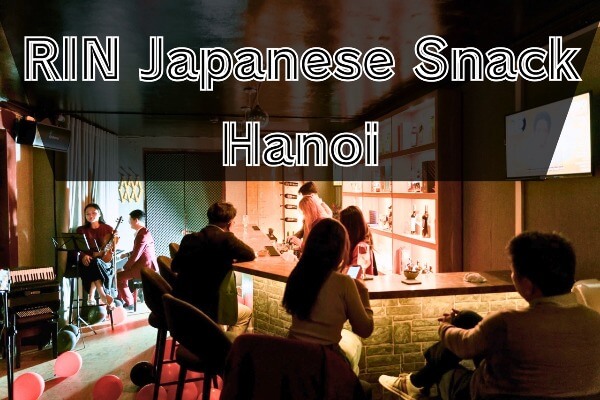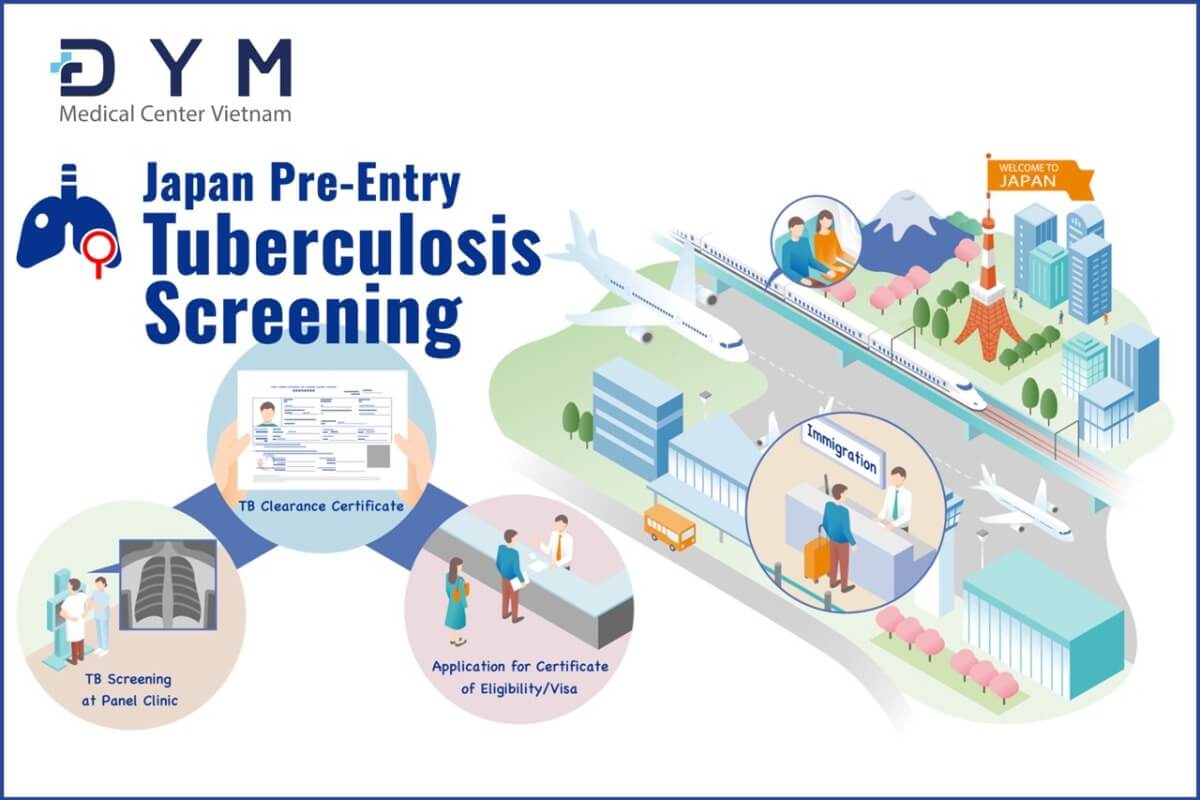おすすめのプロモーション
衰退するベトナム酪農業、ホーチミンでは飼育頭数7割減

<写真:kinhtedothi.vn>
ベトナムの酪農業は深刻な停滞局面に直面している。過去5年間における業界全体の成長率は年間0.4%にとどまり、ホーチミン市では乳牛の飼育頭数が約70%減少するなど、国内各地で衰退の兆しが鮮明となっている。
23日に開催された「乳牛再生産に関する実態と対策」セミナーにおいて、ベトナム大動物畜産協会のルオン・アイン・ズン博士は、国内の乳牛飼育数が約32万6000頭にとどまっており、政府が掲げる2030年までに50万頭へ増加させる目標の達成は困難との見解を示した。
人口1000人あたりの乳牛飼育数は3.3頭であり、これはタイや日本の3分の1、韓国の半分に相当する水準である。ズン博士はホーチミン市のみならず、ハノイ市やフートー省などの中小規模酪農地域においても、今後の持続可能性に強い懸念を表明している。
ベトナム畜産協会のグエン・スアン・ズオン会長もまた、乳製品の国内需要が高まる一方で、原料乳の供給基盤が弱体化している現状に警鐘を鳴らし、「持続可能な乳業の発展には国内の酪農振興が不可欠である」と強調した。
生乳の生産量成長率は、2010〜2015年の年平均17.7%から直近5年では3.3%にまで大幅に鈍化している。
ホーチミン市では現在、乳牛の飼育頭数が約3万7300頭にまで減少し、過去10年間で68.2%、飼育世帯数は72.6%の減少を記録した。同市の畜産・獣医局によれば、都市化の進行により農地、特に牧草地の縮小が進行したことに加え、零細農家が主体であるため生産コストが高く、機械化も進まないといった構造的課題が背景にある。
さらに、国内の加工業者が輸入された粉ミルクに依存し、国内産生乳の調達に消極的である点も、生産者の意欲低下に拍車をかけている。現行法では企業に対して国内原料の使用を義務付ける規定が存在せず、業界内における資源循環が進まない状況が続いている。
こうした中、ズン博士ら専門家は、持続的な酪農振興を実現するための具体的な対策を提言している。その内容には、農家の協同組合化の推進、生産の多様化支援、企業に対する国内原料使用の最低比率(例:5〜10%)の義務化、優遇融資制度の整備や生産設備導入支援などが含まれる。
加えて、政府による持続可能な酪農地帯の再編成計画も、早急に取り組むべき課題として挙げられている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。









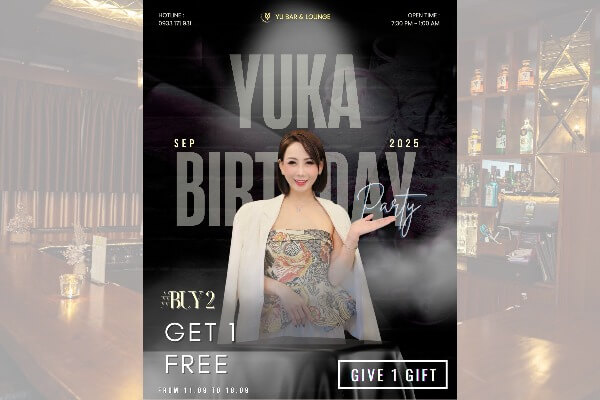






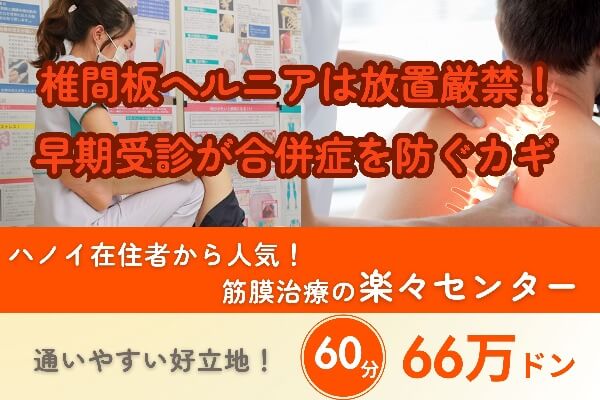
![[飲み放題付き]値段変わらず選べる4種のコース!まる名物を堪能♪](https://image.poste-vn.com/upload/vn/promotion-event-article/promotion_event_article_20250917_1758103973.8193.jpeg)