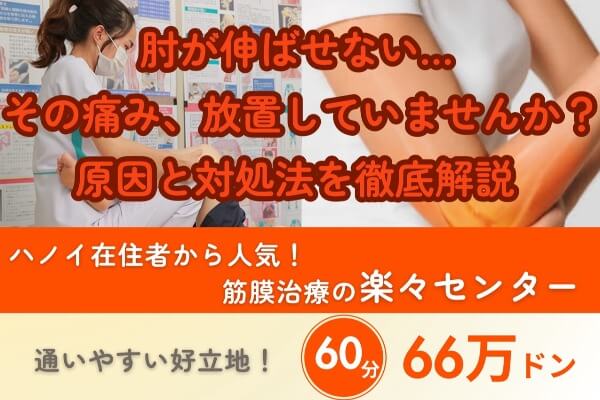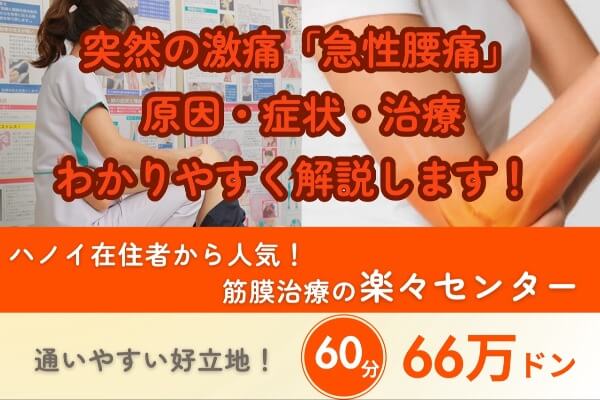おすすめのプロモーション
バインミーによる集団食中毒多発、食品衛生管理の徹底が急務

<写真:baochinhphu.vn>
ホーチミン市において販売されたバインミーを摂取した後に食中毒を訴える患者が続出し、10日午前8時の時点でその数は235人に達した。
ホーチミン市内13の医療機関が対応しており、そのうち96人が入院している。重症例も報告されており、基礎疾患を持つ患者1人は集中治療を受けている状況である。
本件における主な原因として、腸内細菌の一種であるサルモネラ菌の関与が強く疑われている。
患者から得られた臨床データおよび検査結果から、バインミーに使用された具材がサルモネラ菌により汚染されていた可能性が高いとされる。
パテやソーセージ、生野菜、調味料など、加熱や保存の管理が不十分であったことが指摘されている。
食品科学の専門家であるグエン・ズイ・ティン氏は、特にパテの危険性を指摘している。
パテは高栄養である一方で腐敗しやすく、製造工程での加熱不足や、その後の常温保存が細菌の繁殖を助長する。
実際、パテは実験用の細菌培養にも使用されるほど菌が繁殖しやすい食品であり、衛生管理が不徹底である場合には深刻な健康被害を引き起こす恐れがある。
また、バインミーに使用される冷えた肉類や卵の具材が再加熱されずに提供されるケースも多く、これがさらなる汚染リスクを生む。
大規模な販売店舗では、衛生管理体制の不備が多人数への影響につながるため、特に厳格な対応が求められる。
サルモネラ菌への感染は、下痢、腹痛、発熱、悪心といった症状を引き起こす。
健康な成人であれば数日から1週間で自然回復することが多い。
しかし、高齢者、乳幼児、基礎疾患を有する者にとっては重症化のリスクが高く、場合によっては敗血症や腎障害を経て死に至る可能性も否定できない。
このような事態を受け、食品衛生当局は、ストリートフードを含む集団給食向けの食品安全管理ガイドラインの策定を進めている。
原材料の選定、保管、調理、提供方法、さらには食中毒発生時の対応体制に至るまで、包括的かつ実効性のある衛生管理体制の構築が急がれている。
特に、リスクの高い食品に対する取り扱い指針の明確化が重要である。
ベトナム保健省食品安全局は、原因食品の追跡調査を指示するとともに、法令違反が確認された場合には厳正な処分を行う方針を示している。
さらに、再発防止策として、食品の流通過程における温度管理の徹底、衛生基準の遵守、営業許可条件の厳格化などが必要であるとの見解を表明している。
ホーチミン市の一部バインミー業者は、パテやハム類の冷蔵配送、売れ残り品の廃棄といった対応を開始している。
しかし、依然として市場には品質や出所が不明確な食材が多く流通しているのが実情である。
とりわけ、路上販売業者の多くは十分な衛生設備を持たず、高温多湿の気候条件の下で食品が汚染されやすい環境にある。
今回の集団食中毒事件を教訓に、食品の製造から販売に至るすべての過程において衛生管理の徹底が強く求められる。
加えて、行政による監視体制の強化と、食品衛生に対する社会全体の意識改革が急務である。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。