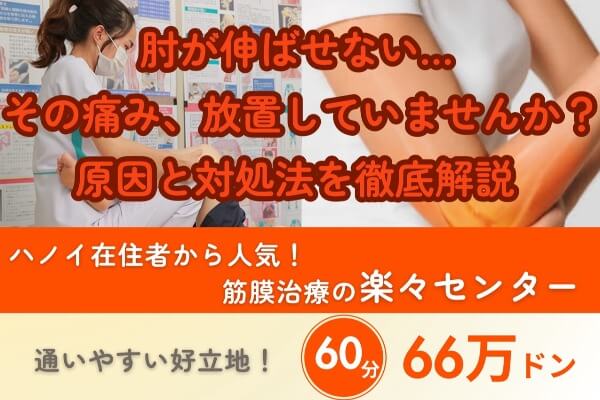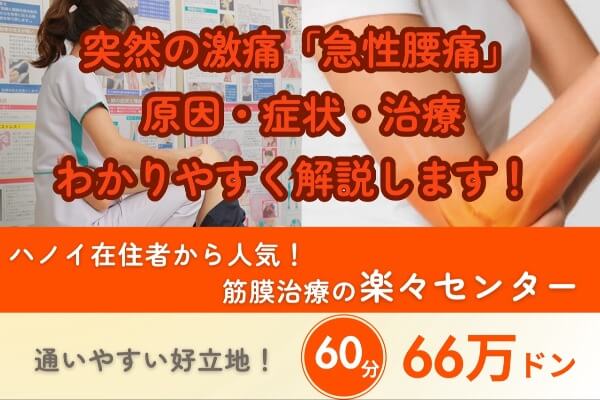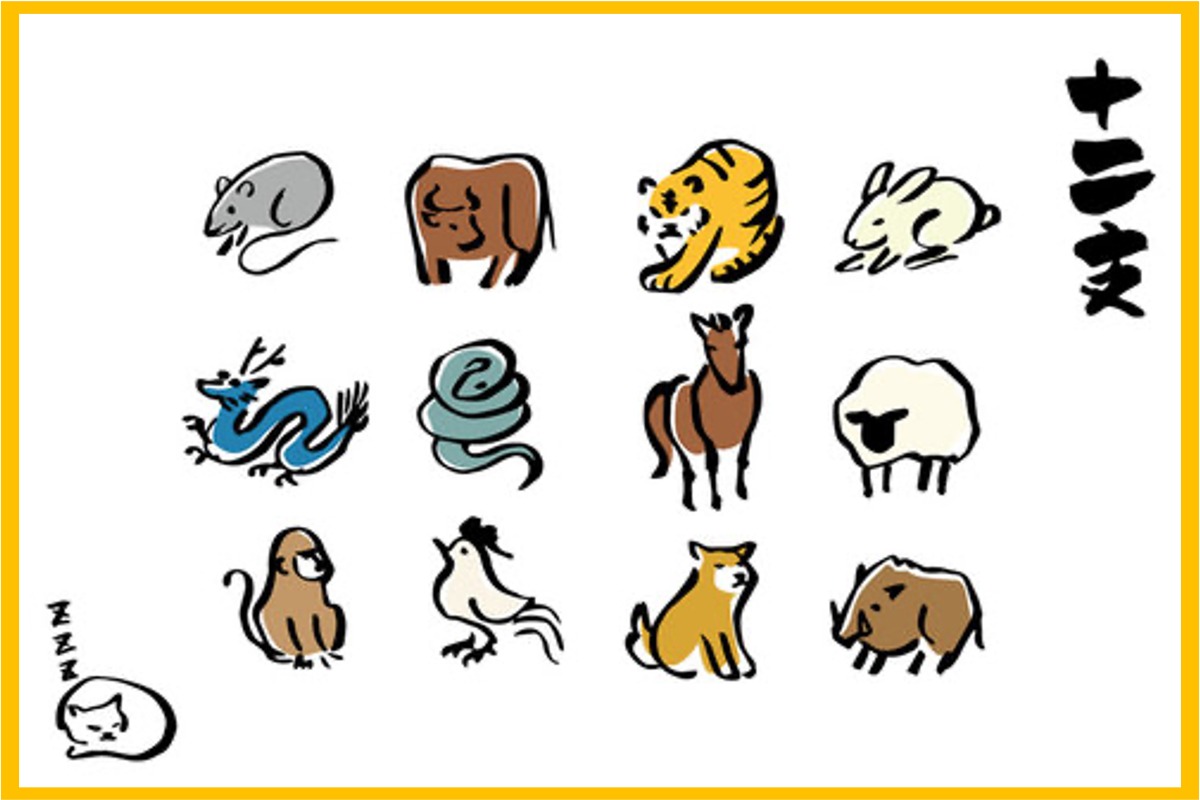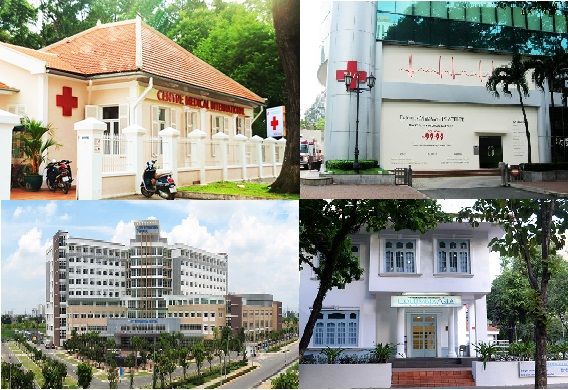おすすめのプロモーション
ハノイ市内の広域冠水、豪雨と排水インフラ未整備が要因

<写真:cafef.vn>
ハノイ市内各地では25日夜から26日にかけての集中豪雨により、深刻な冠水が発生した。
排水インフラの未整備と、既存の設計基準を大幅に上回る降雨量が、広範囲かつ長時間にわたる冠水の主要因となった。
ハノイ排水公社の発表によれば、26日午前7時の時点で市内には80か所以上の冠水地点が確認され、一部では水深が1mに達した。夜までには26か所において冠水が継続していた。
今回の集中豪雨では、一部地域で24時間降雨量が300mmを超え、特にハイバーチュン区では460mmを記録した。
この異常な降雨は台風カジキの外縁部に加え、北中部を通過する熱帯収束帯および太平洋高気圧の湿った東風の影響によるものである。
この降雨により排水インフラの処理能力の限界が露呈した。
現在、排水システムが整備されているのは、ホアンキエム区、バーディン区、ドンダー区、ハイバーチュン区の旧市街地域(トーリック川流域)のみであり、その設計上の処理能力は310mm/2日である。
今回の降雨量はこの数値を大幅に超過し、排水機能の限界を引き起こした。
旧市街地域では、排水管の多くが1954年以前に設置されたものであり、長年の都市化に伴う地盤沈下や油脂廃棄物による詰まりが問題視されている。
ハノイ市当局は飲食店に対し油水分離装置の設置を義務づけておらず、これが排水機能の低下に拍車をかけている。
また、都市化が進行するカウザイ区やナムトゥーリエム区などの新興地域では、排水網や調整池の整備が大きく遅れており、地盤の低さと道路舗装の進行が自然排水を阻害する要因となっている。
これらの地域では排水を自然流下に頼っているが、河川水位の上昇により排水先が失われる事例も確認された。
さらに、ハノイ市全体で過去20年にわたり緑地や水面の面積が大幅に減少しており、市民による排水口へのゴミ投棄や蓋の閉鎖といった行為も、冠水の長期化に寄与しているとされる。
専門家は都市化の進展に見合った排水インフラの抜本的な再設計が不可欠であるとし、あわせて市民の排水に対する理解と意識向上も急務であると指摘している。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。