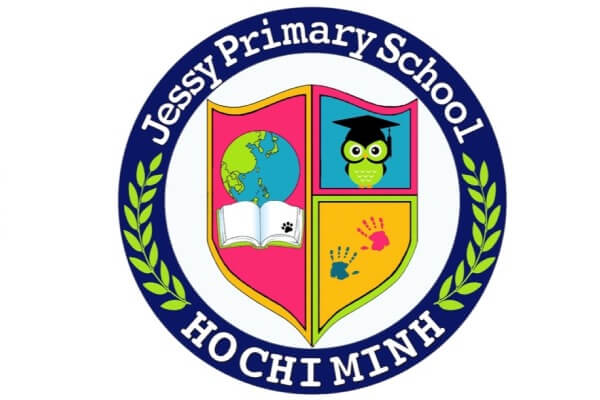おすすめのプロモーション
塩分過多のベトナム料理、過剰摂取の背景と健康リスク

<写真:laodong.vn>
ベトナムの食文化において塩辛い味付けは長年にわたり定着しており、乾燥魚や発酵食品、各種調味料が日常的に使用されてきた。
このような食習慣は、高温多湿な気候や保存技術が未発達であった時代の生活環境に根ざしている。
国立栄養研究所(2021年)の報告によれば、ベトナム人の1日あたりの平均塩分摂取量は9.4gに達しており、世界保健機関(WHO)が推奨する1日5g未満という基準を大きく上回っている。
そのうちおよそ70%は、調理や食事中の調味によって摂取されているとされる。
ホーチミン市医科薬科大学病院の医師によれば、ベトナム人がしっかり味付けされた料理を好む傾向は、文化的に深く根付いている。
冷蔵技術が未発達であった時代には、食材を保存する手段として塩漬け、乾燥、発酵が一般的であり、それらの食品が日常的に食卓に並ぶことで、塩味の強い味付けに慣れる風土が形成された。
また、過去の貧困期においては、少量の塩辛い副菜で大量の米飯を食べるという実用的な食習慣が一般的であり、このスタイルが現代にも受け継がれている。
さらに、地域によっても味の傾向には違いが見られ、中部では塩味と辛味が強調され、北部では旨味を重視した濃い味付けが好まれる傾向にある。
近年では、工業的に製造された調味料の普及や加工食品の増加が、塩分摂取量の増加に拍車をかけている。
うま味調味料、即席麺、ソーセージなどの加工食品は強い味付けが特徴であり、これらは味覚を麻痺させるとともに、依存性を高める要因にもなり得る。
高塩分の食事は、健康に対して深刻な影響を及ぼす。
高血圧、心筋梗塞、脳卒中、腎機能障害、胃がん、骨粗しょう症などのリスクが指摘されており、とりわけ小児期から塩辛い味に慣れることが、将来的な健康被害につながる可能性がある。
ベトナム保健省は、2030年までに国民の塩分摂取量を30%削減するという目標を掲げ、啓発活動を展開している。
専門家は、急激な減塩ではなく、香味野菜やハーブといった天然の素材を活用した段階的な減塩が効果的であると提言している。
食文化に深く根ざした習慣を変えるには時間と努力を要するが、健康を守るためには、まず日常の調味行動を見直すことが重要である。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。








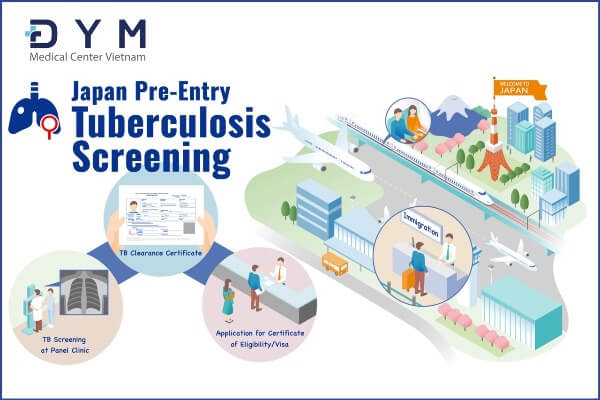







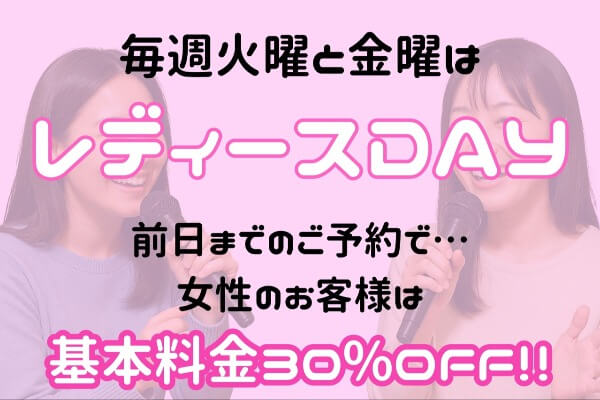











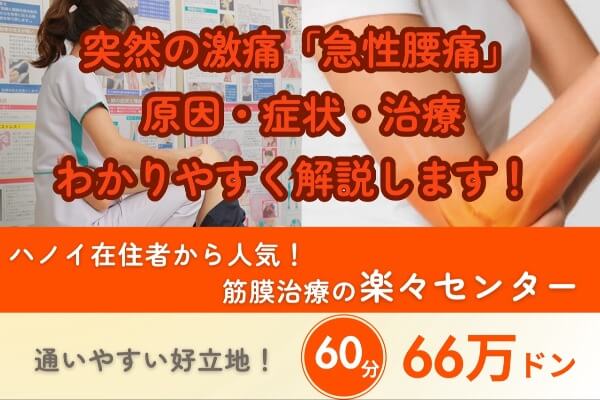
























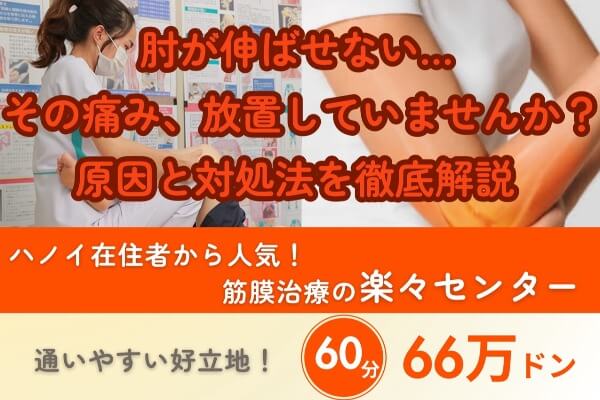












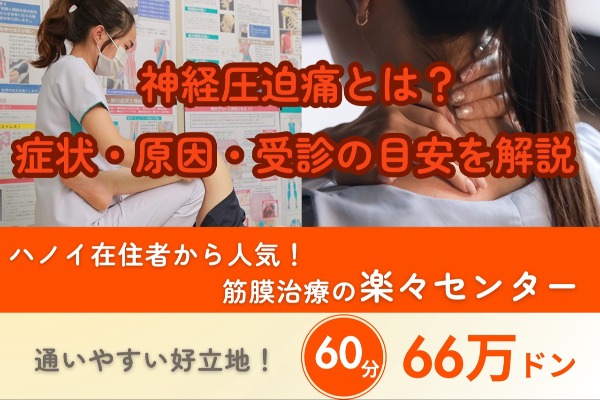


![[食肉卸]独占輸入・飲食店必見! 宮崎のブランド鶏をHCMCで](https://image.poste-vn.com/upload/vn/lifetip-article/lifetip_article_20250829_1756435949.8758.jpeg)