おすすめのプロモーション
ホーチミンで深刻化する地盤沈下、世界有数の沈下速度を記録

<写真:moitruong.net.vn>
ホーチミン市は、地下水の過剰採取、脆弱な地盤構造、急速な都市化といった複合的な要因により、世界でも最も地盤沈下が進行している都市の1つに数えられている。
環境省が2020年に発表した気候変動シナリオでは、ホーチミン市およびメコンデルタ地域が国内でも特に沈下の顕著な低地とされている。
2005年から2017年にかけて、ホーチミン市の地盤は年平均で約2cm沈下し、累計では23cmに達した。
シンガポールの南洋理工大学、NASA、スイス連邦工科大学による国際共同研究においても、同市は地盤沈下の深刻な都市の1つとして名指しされている。
地盤沈下の主因は、自然的要因と人為的要因の両方に起因している。
自然的側面として、ホーチミン市は若い沖積層の上に形成されており、泥や粘土、泥炭などの堆積物が多く、7区、8区、ビンチャイン郡、ニャーベー郡などで特に地盤が脆弱である。
さらに、地下水位の季節変動や高潮、塩水の侵入も沈下を助長する要因となっている。
人為的な側面では、長年にわたる無秩序な地下水採取が深刻な影響を及ぼしてきた。
2010年時点で市内には20万本以上の井戸が存在し、地下水の採取量は日量で100万m³を超えていた。
これは当時の政府計画の5倍に相当し、複数の地区では最大20cmの地盤沈下を引き起こしていた。
この状況を受け、市当局は2012年に地下水利用の規制を導入し、2025年までに採取量を日量10万m³以下に削減する目標を掲げた。
同時に、使用許可制度の強化、使用料の徴収、古井戸の埋設処理などの対策も講じられてきた。
都市化の進行も沈下を加速させる要因である。
2011年から2017年までの都市化率は平均80%を超え、2018年から2022年にかけても78〜80%の高水準を維持している。
地表がアスファルトやコンクリートで覆われることにより、雨水の地中への浸透が妨げられ、地下水の自然な補給が困難となり、地盤の収縮と不安定化が進行している。
InSAR(合成開口レーダー干渉法)を用いた観測では、南サイゴン、タインダー半島、ヒエップビンフオック、タオディエンなど、サイゴン川沿いの低地かつ地盤の弱い地域で特に著しい沈下が確認されている。
専門家らは、まず地盤沈下を常時監視する定点観測ネットワークの整備が必要であるとして、科学的データに基づく都市計画の策定を求めている。
沈下が進行している地域では、従来型の開発手法ではなく、地形に適応したインフラ整備や経済活動への転換が求められている。
さらに、水を貯える都市公園や調整池の整備、豪雨や高潮に柔軟に対応できる排水システムの構築も有効な対策とされている。
経済発展と環境問題が交錯するなか、ホーチミン市は地盤沈下という新たな都市課題への対応を迫られている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。


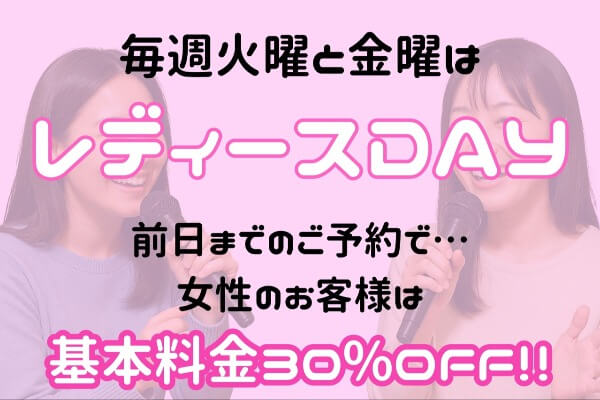















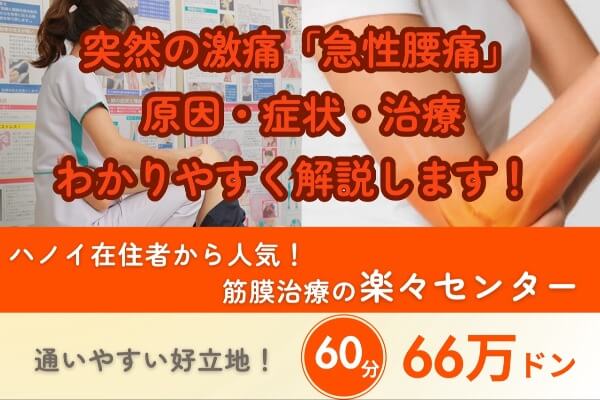














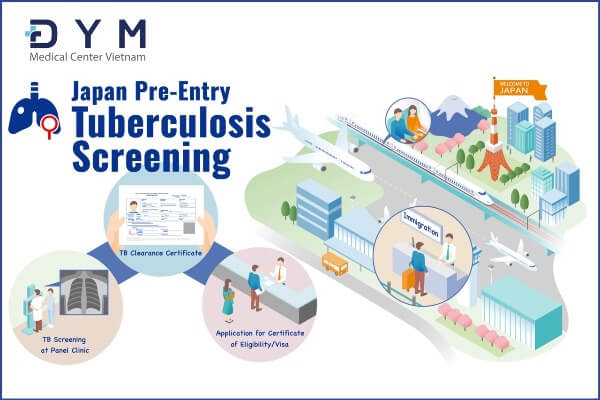




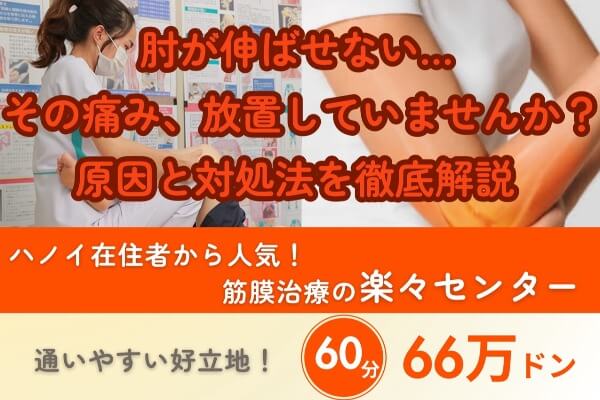








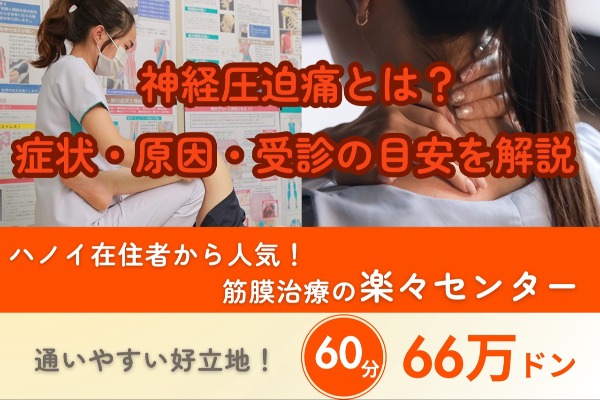






















![[食肉卸]独占輸入・飲食店必見! 宮崎のブランド鶏をHCMCで](https://image.poste-vn.com/upload/vn/lifetip-article/lifetip_article_20250829_1756435949.8758.jpeg)











