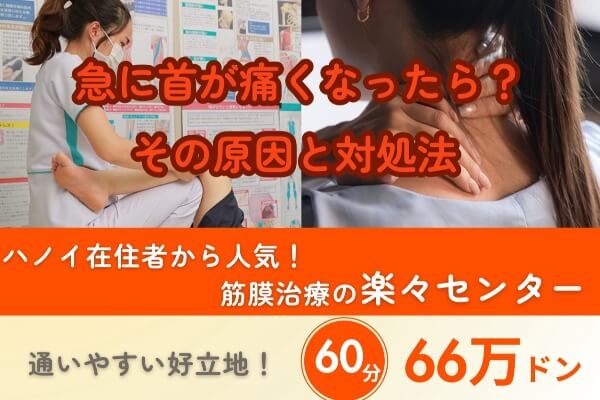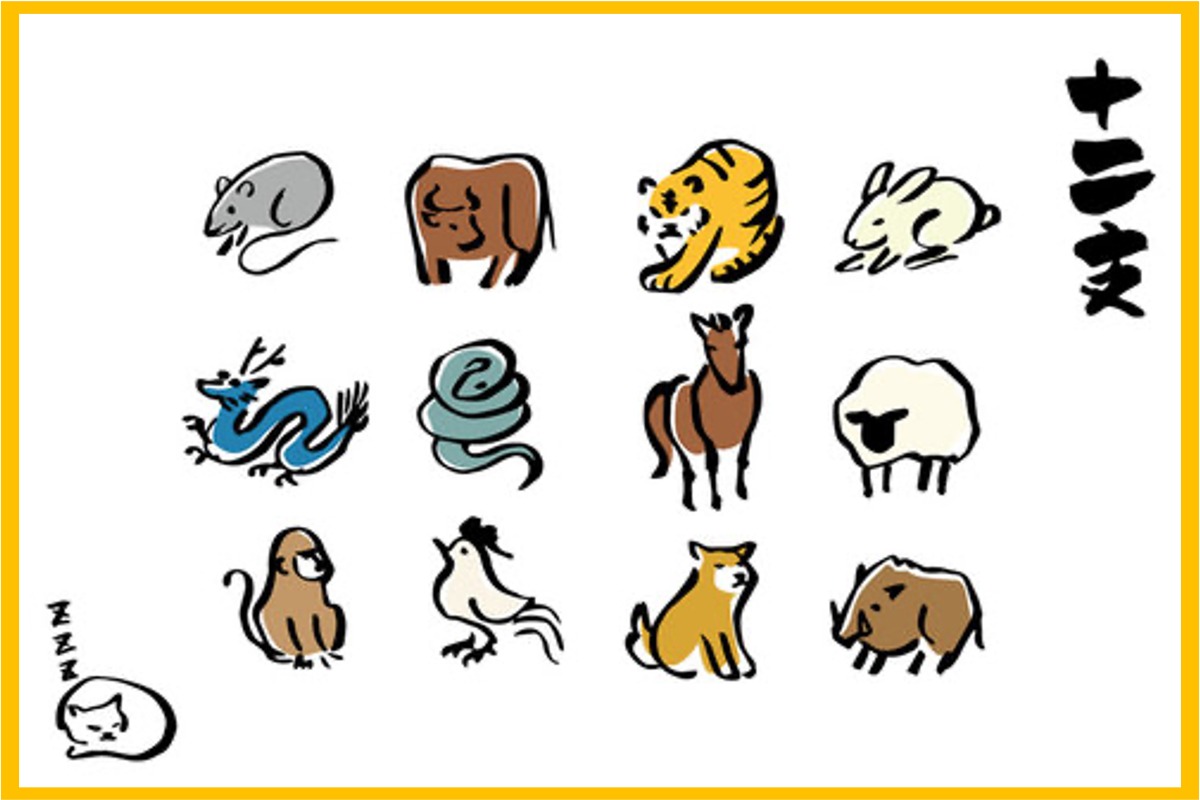おすすめのプロモーション
AI依存の落とし穴、ベトナムで進むChatGPT活用に警鐘

<写真:huengaynay.vn>
ベトナムにおいて、生成AI「ChatGPT」の利用が医療や教育といった専門性の高い分野にも広がる中、その過信によるリスクが懸念されている。
専門家らは、利便性の裏に潜む誤情報や依存傾向に対して強い警戒を示している。
ある65歳のベトナム人男性は、喉の痛みと軽い咳を訴えた際に医療機関を受診せず、ChatGPTに症状を入力して診断と処方を求めた。
AIの回答を「医師よりも客観的で詳しい」と信頼し、健康相談に繰り返し利用していた。
しかし、後に腹痛を訴えた際にもChatGPTの「軽い消化不良」という診断を信じて放置した結果、実際には胃出血を起こしていたことが判明した。
ハノイ市では、不動産の価格交渉にChatGPTのアドバイスを活用する例や、宿題をAIに全面的に依存する学生など、日常生活のさまざまな場面でAIへの依存が進行している。
このような傾向に対し、デジタル転換の専門家は「AIの利便性により、専門家の役割をAIが代替可能と誤認するケースが増加している」と警鐘を鳴らす。
心理学者も「無料で常時利用可能なAIは、経済的負担を抱える人々や、些細な疑問を相談しにくいと感じる層にとって特に魅力的に映る」と分析している。
米OpenAIによれば、ChatGPTの週次利用者数は世界で2億人を超える。
ベトナム国内では、2025年上半期における生成AI関連アプリの利用時間が2億8300万時間、アクセス回数は75億回に達したという。
一方で、誤診や誤情報による被害も各地で報告されている。
イギリスでは、AIの助言を受けて食塩の代わりに臭化ナトリウムを摂取した高齢者が中毒を起こした。
ベトナムでは糖尿病患者がAIの提案を鵜呑みにして薬の服用を中断し、昏睡寸前まで状態が悪化した事例も明らかになっている。
教育分野においても問題は深刻化している。
ハノイ市在住の高校生は、ChatGPTの利用を始めてから家庭学習の時間が大幅に減少し、試験成績が最低水準にまで低下した。
保護者によると、教師から「最も学力が低い生徒」と指摘されたという。
こうした事態を受け、専門家らはAIの活用に際しては明確な目的と限界の認識が不可欠であると強調する。
情報の真偽を自ら見極め、判断力を養うことが重要であり、AIは依存の対象ではなく、自身を成長させるための起点であるべきである。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。







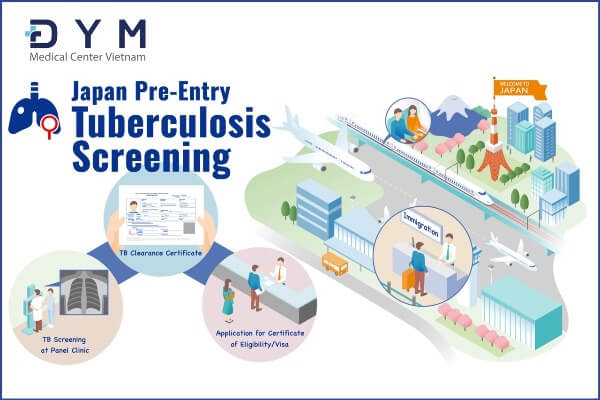























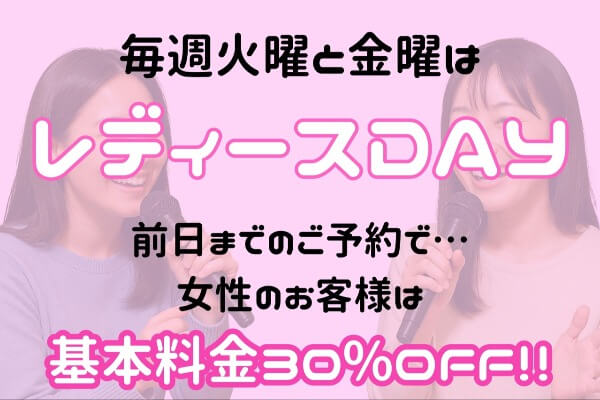




















![[妊婦さん必見]妊娠時期別の時期別の歯科治療ガイド|ありが歯科](https://image.poste-vn.com/upload/vn/promotion-event-article/promotion_event_article_20251006_1759738693.9821.jpeg)



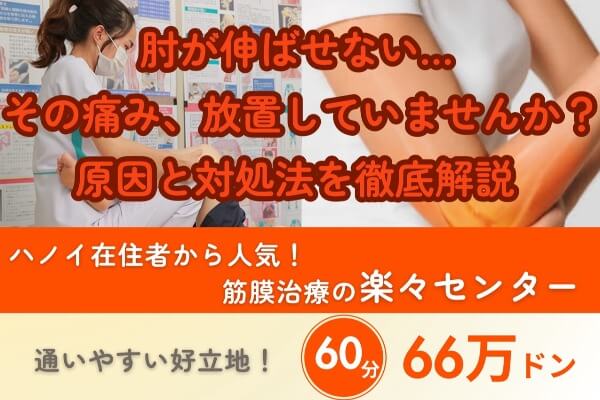


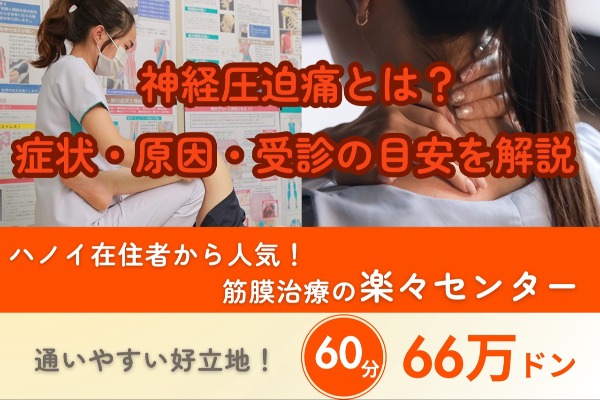



![[飲み放題付き]値段変わらず選べる4種のコース!まる名物を堪能♪](https://image.poste-vn.com/upload/vn/promotion-event-article/promotion_event_article_20250917_1758103973.8193.jpeg)