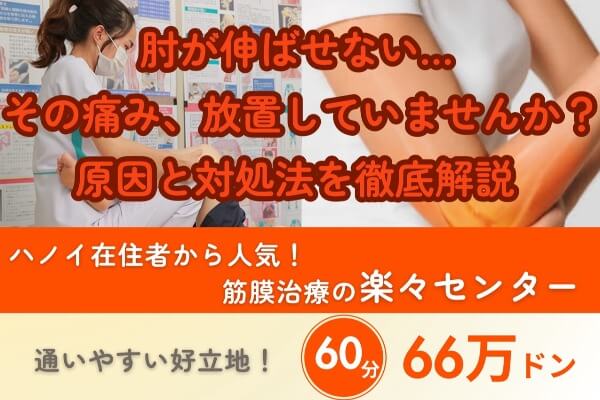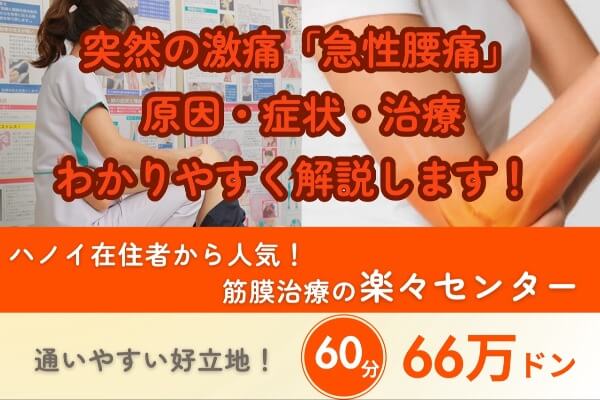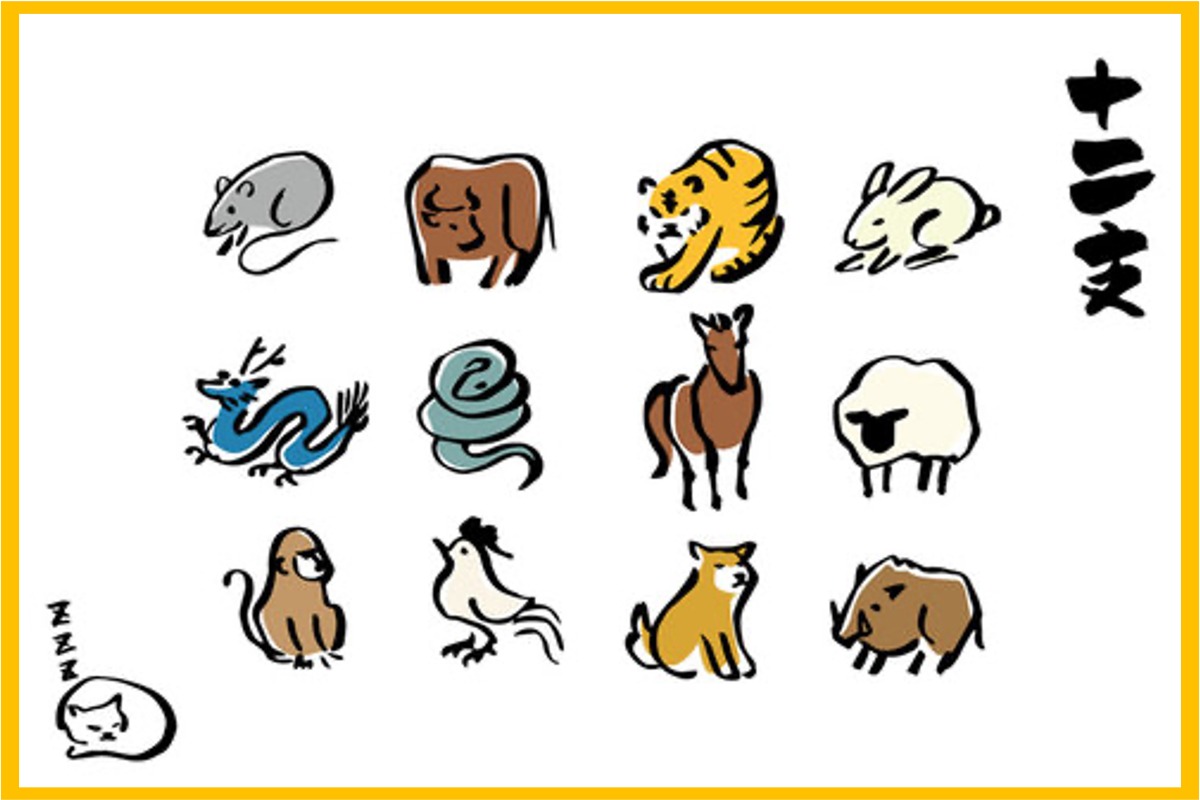おすすめのプロモーション
ホーチミンで深刻化する住宅取得難、中間所得層の現実

<写真:plo.vn>
ホーチミン市において、中間所得層の住宅取得がますます困難となっている。
商業住宅の価格は急激に上昇しており、それに対して社会住宅の購入条件を満たさない市民が相次ぎ、住宅を所有するという夢が一層遠ざかっている状況である。
政府が定めた政令第100号では、独身者の月収が1500万ドン(約8万3850円)、夫婦合算で3000万ドン(約16万7700円)を超えると社会住宅の購入資格を失う。
この基準は従来より月額400万ドン(約2万2360円)引き上げられてはいるが、依然として多くの労働者が対象から外れている。
たとえば、ある女性は月収1700万ドン(約9万5030円)を得ているが、社会住宅の資格を持たず、商業住宅は高額で手が届かないという。
借入可能額と家族からの支援を合わせても16億ドン(約894万4000円)が限界であり、市内でこの価格帯に該当する物件はほぼ存在しないとされる。
不動産調査会社CBREの報告によれば、2025年第一四半期におけるホーチミン市の新築分譲住宅の平均価格は、1㎡あたり7700万ドン(約43万430円)に達している。
中古物件も5100万ドン(約28万5090円)を超えており、月収1500万ドン(約8万3850円)程度の労働者にとっては、住宅購入は極めて困難な課題である。
ホーチミン市の不動産市場は、アジアでも特に手が届きにくいと評価されている。
不動産業界では、価格高騰の背景に新築物件の供給不足や、一部投資家による価格操作があると指摘されている。
中古物件でも実勢より高値で販売される例が多く、購入者が意図せず価格操作に巻き込まれるリスクが存在する。
住民間で価格を比較した結果、購入後に「高値掴み」に気付くといったケースも報告されている。
不動産専門家によると、価格の異常な上昇は、内部取引や意図的な価格吊り上げの影響であるという。
また、収益性が低く、頻繁に売買されてきた物件や、ある特定の地域に突然関心が集中する事例は、価格操作の兆候とされている。
ベトナム不動産協会は「労働者の住宅問題を解決する鍵は、手頃な価格の物件を十分に供給することにある」と述べ、政府による低価格住宅の建設支援や、中間所得層および若年層に向けた金融優遇策の導入を訴えている。
加えて、ホーチミン市不動産協会は、中間所得層を対象とした新たな優遇ローン制度の創設や、社会住宅の購入条件を地域の実情に応じて見直す必要性を提起している。
現行制度は都市部の生活実態と乖離しており、多くの市民が制度の恩恵から取り残されているという。
今後、ホーチミン市においては、住民の購買力に見合った住宅供給体制の整備が喫緊の課題となっている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。